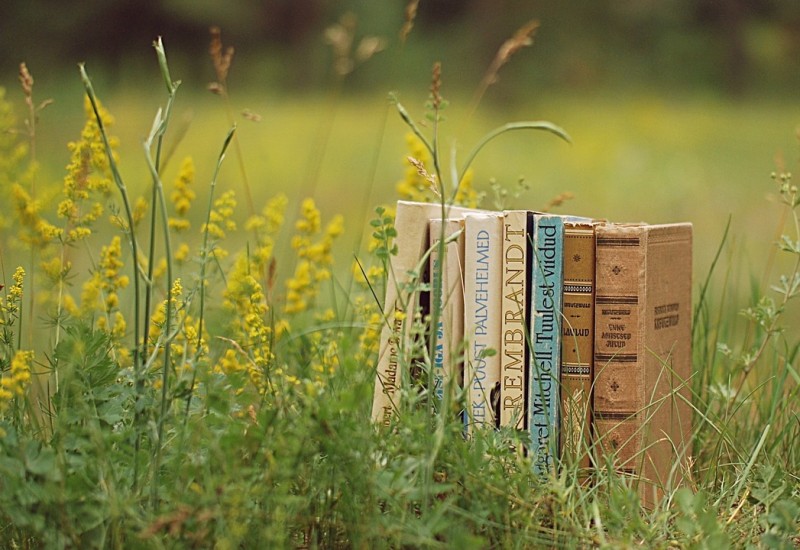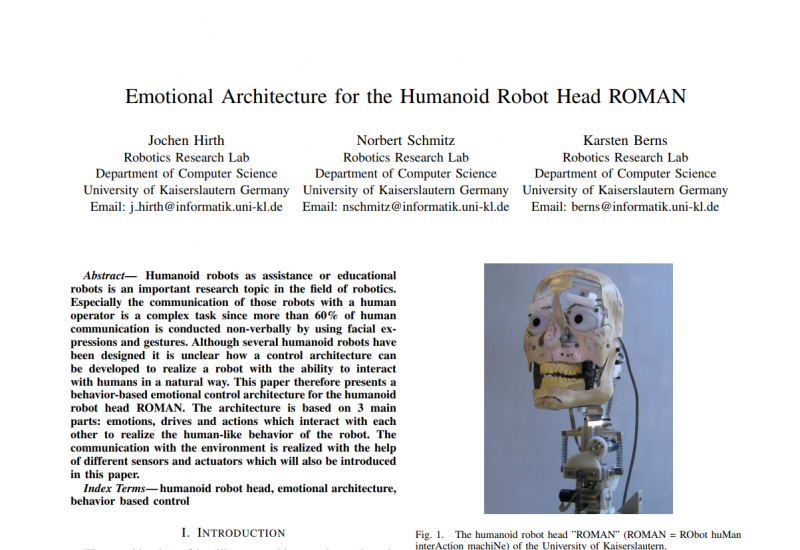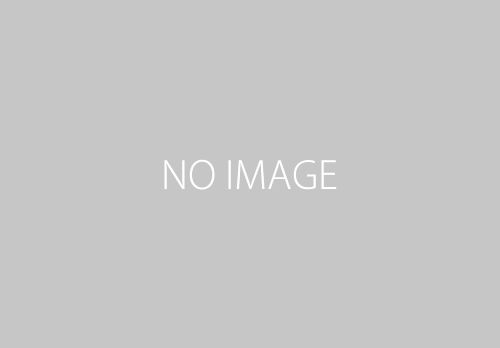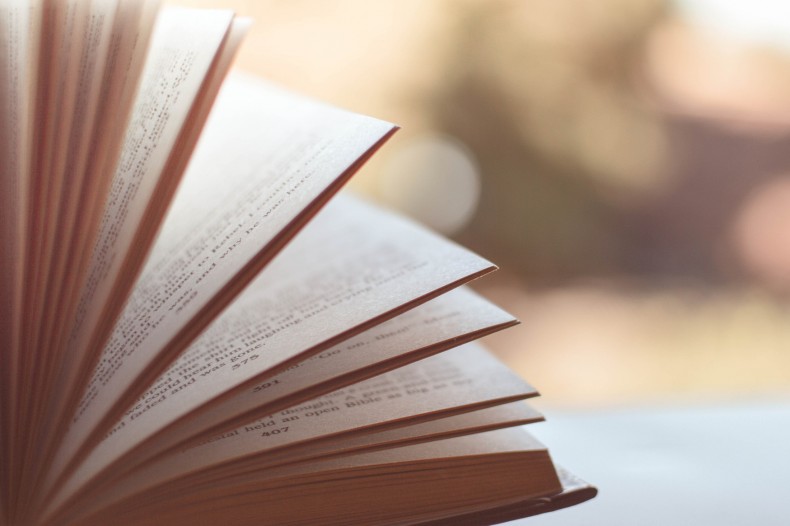定例研究ミーティングでの報告の仕方

研究技術解説
[:ja]
ここでは毎週の定例研究グループミーティングで実施する内容と実施方針についてまとめます(2016年1月版です.今後修正の可能性があります).定例ミーティングの最も大事な目的は,各々の次の行動プランを確定させることです.基本的には各メンバーからの進捗報告を中心にミーティングを構成します.進捗報告は下記の4点で要点を抑えて,最低限の情報で簡潔になるように心がけましょう.目安は一通りの説明に5分です.形式はPowerpointでも,Wordでも,Evernoteでも構いません.内容に合わせて最も伝わりやすいと判断した形式を採用してください.
他の研究技術記事一覧はこちら.
- 件名,問題名
- 「何が」「どうなのか」を明確にする
- 「~の動きが安定した件」「~のデータが膨大すぎる件」「~のノイズ大き過ぎ問題」など
- 「~の論文を読んだ件」などでもよい
- 「月曜から夜ふかし」方式がわかりやすい
- 月曜から夜更かしまとめ http://takeshiigaku.com/
- 「何が」「どうなのか」を明確にする
- 結論
- それぞれの件について「どうなったのか」の報告
- 「この対処で劇的に(~%)改善した」「2通りの処理のどちらから優先して取り組むか悩んでいる」「この方法によってノイズが~%低減した」など
- それぞれの件について「どうなったのか」の報告
- 理由・経緯
- 結論に至った経緯の報告
- なぜその問題が生じたか,なぜそれが問題なのか
- 「~ができる程度に安定させないと~ができない」「データが~種類あり,それぞれに~項目のデータがあるため」「ノイズをこの程度に抑えないと~がうまくいかない」など
- なぜその対処方法を選択したか,具体的に何を行ったのか
- 「3通り試した」「この論文で2通り紹介されていた」「簡単な装置を作って試験した」など
- 結論を下すのに用いた結果は何か,それをどのように解釈したのか
- グラフ化したり,統計処理を施したデータ
- 実物や動画などでもよい
- なぜその問題が生じたか,なぜそれが問題なのか
- 結論に至った経緯の報告
- 個人的所感・感触
- 上記1~3までには,根拠のない主観は極力混ぜない
- 根拠は薄いが,それぞれの件についての意見や提案などは最後にまとめる
- 次の行動プランも表明する
上記の報告を一通り聞いた上で,全体で話し合って次の行動プランに対する判断を下します.より詳細な説明が必要になる場合があるので,上記の要点から省いた関連資料やデータも用意しておいてください.簡単には解決できないような問題が生じていたり,次の行動プランが決められない場合には,上記とは別に,下記に挙げる議論の準備をしておいてください.
- 問いの形で相談したいテーマを明確に投げかける
- 「~の動作を安定化させるにはどうしたらよいか?」「~を反映しつつ情報を落とすにはどうしたらよいか?」「~のノイズを減らすにはどうしたらいいか?」など
- 意見を集めるための複数の論点を先に挙げておく
- 「原因の見つけ方」「対策の打ち方」「対策の効果の評価の仕方」「現手法の問題点」など
論点まで準備がされていれば,意見が出やすいです.各論点ごとに出た意見を通じて,次の二点を実施しましょう.
- 複数意見をまとめて「つまり,こういうことですね」という結論を自分で下して確認をとる
- 下した結論に基づいて,「では,次はこうしてみます」という次の行動プランに落とし込む
行動プランが決まったら,実行し,その結果を次のミーティングで再度上記の方針に沿って報告をしてください.
[:]